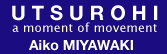 |
|||||
宮脇愛子との対話
太田泰人
── 今回の展覧会は,宮脇さんの40年間のお仕事を初期から今日まで「時代」を追って「回顧」してみようという意図があります。けれども、同時に私たちはその軌跡を通じて驚くほど一貫したなにかがあると感じている。その「なにか」の示すものの感触を、「はじめもなく終りもない」という宮脇さんの言葉をお借りして1)、展覧会のタイトルに表したわけです。
そのときに私たちの念頭に当然浮かんだもうひとつのキーワードとして「うつろひ」というのがあります。これは最近の宮脇さんの仕事を貫く言葉というか、コンセプトとして機能していますが、そこらあたりからお話を始めさせていただきたい。あの言葉は、1978年に磯崎新さんのオーガナイズで、パリで開かれた「日本の時・空間ー〈間〉」2)の展覧会の時に最初に出てきたのですよね。
── そうです。あのときは、ワイヤーではなくて真鍮の作品でした。屏風みたいな金属のもの。〈間〉の展覧会のコンセプトのひとつとして出したのです。でも、それとワイヤーで出来た作品は、かたちはまったく違うけれど、コンセプトは同じだと思います。光にたいする、変わっていく光に対する、ね。
── そのかたちの違いはどこから、どのように生まれてきたのでしょうか。ワイヤーというのは、コンセプトが同じだとしても斬新だと思うのですが。とくに空間に対する関係なんか大きく変わりますね。屋外にも屋内にも自在に対応できるとか、イベント的に設置の自由なあり方ができるとか。辻邦生先生のエッセイもそのあざやかな変身の感触をお書きになっていますね。
── やっぱり、なるべく彫刻的な重さとか、物量的なものとかを排除して、なるべくそぎ落としたような材料を捜していたわけです。それで、たまたまピアノ線ていうのが見つかった。堀内正和先生が「のみの夫婦がとんだ」とお書きになっているように、本当に小さなピアノ線から始まったのね。小さい模型です、だから「ぴょん」と。それから、大きいのをみつけるまでが、すごく時間がかかったんです。
一宮の児童公園で作った最初の屋外の作品は、私自身が手で作ったのではなくて、工場でパイプを溶接して作ったんです。それを大きなトラックに乗せて持っていった。その後の私の場合は、長いワイヤーを持っていって、その場所で作品をインスタレーションするというものなんですが、そうじゃなかった。実に不自由なものだった、不自由なかたちになっている。
── するとその頃には、模型のほうに宮脇さんのイメージがむしろ実現されていたわけですね。それで面白いと思ったのは、この最初の模型をさまざまな角度から写真に撮られていることです。わずか数本のワイヤーが置かれるだけなのに、見る角度によって、空間が大きく姿を変えている。私たちの認識の枠をするりとすり抜けて変容していく。で、これってトポロジカルな発想があるんじゃないかと思うんですね。考えてみると、《MEGU》とか《Study of Homology》とか、70年代のお仕事もものの見え方にすぱっとトポロジカルな切り替えを介入させていますよね。《うつろひ》はそれを空間そのものに移したというか。
── そうかもしれませんね。たしかに、あの前の時期にはトポロジー的なコンセプトがありましたから。一番最初の模型が2本のワイヤーでできているのも、他でも説明しているけれど、そういう見方もできますね。あの模型を東京画廊で展覧会に出した。それを堀内先生がご覧になって、中原祐介さんも書いてくださった。大きいワイヤーを捜すのは苦労して時間もかかったんです。ギャラリー・ムカイの向井さんが紹介してくださった村山さんというコレクターの方が、ピアノ線を作っている工場の社長さんだった。習志野に工場があって、そのころわたしのアシスタントだった青年と一緒に行って、そこでピアノ線を見つけて感激しちゃって持って帰ったの。卷いて、満員の電車に乗って。そのピアノ線がみつからなければ、野外彫刻の《うつろひ》は出来なかった。だから村山さんにはすごく感謝している。うれしくて工場の真ん中でさっそく作ったりしたんです。でも最初は、鉄のワイヤーだったんです。鉄だと張力はステンレスよりずっとあるんだけれど、雨に会うと錆びてしまうから野外におけない。
── そういう材料の発見より前から、「空に線を描く」というイメージはお持ちになっていて、ドローイングを続けていらしたわけですね。そうした線を描く、空にカリグラフィをするというのは、子供時代からの自由への夢とつながりがあるとおっしゃっていますけれど、それが「うつろひ」という言葉、コンセプトに結びつくと、「日本的」と言われることもあると思うのですが。とくに牧谿など水墨画が昔からお好きだったとも伺っているのですが。
── そういう東洋的というのは意識していたというよりも、自然に出てきたという感じね。やはり私は日本美術史と西洋史を勉強したわけで、日本と西洋の関係はいつも考えています。けれど作品について「日本的」と言われるのは心外なので、始めの頃は必ず “Utsurohi”のあとに“A Moment of Movement” と言い換えを添えていたわけです。コンセプトとしては、最近の流行のことばで言えば「ゆらぎ」でもいいんです。
── 堀内先生は、「宮脇さんがこんな軽妙で自由な境地に達したのは、パリ滞在中親しくしていたマン・レイからの感化があるのではないかと思う。ダダを通過してきたあの自由人は、ヘンリー・ムーアが重々しい彫刻を作っていたとき、ハンガーを沢山天井からぶら下げ、実に軽妙洒脱な作品に仕上げて遊んでいたらしい」とお書きになっていますが3)。
── いえるかもしれないですね。ちょっとふざけたところね。ふざけたというか、重々しいとかそういうものへの反撥は大いにあった。だから、マン・レイが好きだった。ムーアだって嫌いではないけれど、もちろん。だけど、ミラノに住んでいたときからマリノ・マリーニなんかにも関心はあまりなかった。それにやっぱりアブストラクトの洗礼を私は受けていたから、リアリスティックなものに対する反撥はすごくあったのね。だから「あらぬもの」なんて言ったりしたんですね4)。
── ところで先日、国立国際美術館で「瀧口修造とその周辺」展を見て、1958年という早い時期の絵画作品を初めて拝見したのですが、ずいぶん激しいもので驚きました。
── 化学者でコレクターの大橋さんがミラノの画廊で買ってくださった作品ね。最初はああいうものから始まったんですね。瀧口修造先生が東京の展覧会の時に、あれをご覧になって、あなたはミラノに行ったらいいですよとおっしゃったの。
その前にアメリカに行ったのは留学生として。お友達がカリフォルニアにいて呼んでくれた。UCLAとサンタ・モニカ・カレッジに入って、美術学部に入って絵を描き始めたんです。ヌードデッサンとかもやって。1957年のことです。でも、自分では鳥みたいな、シュールみたいな絵も描いていたんです。日本女子大に行っていた頃から阿部展也さんのところには通っていた。斎藤義重さんは、義理の姉で絵描きだった神谷信子の紹介で、家にいらしたり、斎藤先生のところに行ったりしていました。
斎藤先生はいろいろ助言してくださった。わたしはその頃ひそかに絵を描いていたんです。家には絵描きはひとりで沢山だって言われていたから。神谷信子は、神谷葡萄酒にお嫁にいったのだけど、そこで未亡人になって絵を描いていた。まわりの絵描きたちがいろいろ大変だったんです。それで父が絵描きはひとりで沢山だと。だから私はこっそり絵を描いていた。ところが、斎藤先生がいらして、絵はぜったいこっそり描いては駄目だというの。人に見せなければ駄目だと。だから斎藤先生は恩人なんです。
── それで、59年の養精堂の展覧会での作品は、シュール的というか、まだ激しいうねりのようなものがあったと思うのですが、それと平行してすでにウニスム的な純化された表現もあったのですか。
── ポーランドのスチュレミンスキーやコブロたちのウニスムの運動については、阿部先生が資料をお持ちだったの。私にはぴたっときたのね。それ以来、ポーランドは大好きな国です。
── それはイタリアに行かれる直前ぐらいですか。
── そうですね。
── イタリア行きの前にすでに抑制された画面、ウニスム的なものになっていたのでしょうか。
── そうです。でも、それは行ったり来たりね。非常にシュール的なものとの混合ですよね。もっと点描みたいな絵も描いていた。いろんな色の。鳥をイメージしてたのね。でもイタリアに行って、マンゾーニとかフォンタナたちの中に入ってみて、ますます自分の気持ちがはっきりしていった。彼らもウニスムの影響をすごく受けているのがわかったんです。はっきりとは言ってなかったけれど。ドイツの「ゼロ」のグループなんかもそうでしょう。ヨーロッパの連中にウニスムはすごく影響があった。
── 先年、その当時の絵がまとめて再発見されて話題になりましたね。ただ、その時にちょっと疑問に思ったのは、これまでも宮脇さんの初期の絵画は、しばしば展覧会にも出品されているし、高く評価もされているのに、どこが「再発見」なのだろうということです。それで、この点をもう少し詳しく伺いたいのですが、たとえば、1960年前後の作品は何種類かありますよね、網の目だけのものとナイフで塗り重ねた絵の具の垂れの繰り返しもようなもの、両方が重なり合って見えるものと。単位要素の反復といっても違いがあるような気がするのですが、それらはどのような関係にあったのでしょうか。
── ようするに網の、なんでもない絵ですよね。だから、東京画廊の山本さんが「あんな破れ畳みたいな絵が売れるか」って言ったのは非常にあたっている。その当時としては。最初はね、「破れ畳」の上にあれをやっていたの。そういうプロセスなの。その最初の下地として「破れ畳」を使った、ヴィジュアルな意味で。それを途中から下地だけにしちゃったわけです。
── ということは時期的には入り混じっているわけですね。
── そうなの。あの頃は、やみくもにそういう連続したものに興味を持っていた。原宿の元子爵の奥さんが持っていた家に部屋を借りていて、そこの庭でたくさん絵を描いたの。大切な庭石に絵の具を垂らしたりして。
── 1962年の東京画廊の展覧会の序文で高階秀爾先生がカタログの序文を書かれていて、緑の色彩とか、燃え上がる情念的なものとかに注目されているようですが5)。
── 高階先生は独特の観点からご覧になったんでしょうね。高階さんは1959年の養清堂画廊の個展の時に最初に私の作品について美術雑誌の『みづゑ』に書いてくださったの。パリから帰国されたばかりでわりとほめてくださったのよね。
── すると宮脇さんの動きとしては、1959年のミラノから東京にいったん戻り、作品を作り、1962年のはじめに展覧会をやり、それからもう一度パリに出かけられたわけですね。
── 1962年に東京画廊でやったときに、フランスの画商のアンドレ・シェレールが買ったんです。東京画廊に見に来て。フランスと交換展をやるつもりで、東京画廊の全体の中から何人か作家をピックアップしていく予定だったのだけど、私の作品が気に入ってくれた。アンドレ・シェレールはその頃大変な人だったんですよ、現代美術の旗手みたいな。当時、東京画廊には斎藤義重先生をはじめとしてえらいアーティストがたくさんいて、私などは一番底辺だったんだけど、それをフランス人って意固地だから、これと決めたら強情でしょう。みんなは私が若い女だからなんて言ったけど、わたしには会う前に決めたんです。10点ぐらい買って持っていった。それで私は、アンドレ・シェレールに招待されてというか、雇われて、1年間パリに滞在して作品を作り展覧会をやるという契約をして行ったんです。日本では当時、ちょっとした事件でした。
── するとパリでマン・レイに会われたというのはいつなのですか?
── 最初に会ったのは59年ミラノにいたときに、ハンス・リヒターがたまたまパリに行くから一緒に行くかと言うから、パリに行き、マン・レイのアトリエをちょっとだけ訪ねた。62年にアンドレ・シェレールと契約してパリに行ってからは、マン・レイと毎週毎週つき合いました。それと、私はヴァン・ドゥースブルクの奥様、ネリーのところにも年中遊びに行かせてもらって、それもとても楽しかった。ヴァン・ドゥースブルク設計のムードンのアトリエに毎週のように行って。ネリーからは本当に色々な話を聞きましたね。
── アンドレ・シェレールは、フォートリエとかメッツァンジェとか、いわゆる叙情的抽象やアンフォルメルを押していた画廊ですよね。それで、もう一度、平面の作品の話に戻りますが、山口勝弘さんが画面にあてる照明の光を動かしてみせると面白いとおっしゃったのはいつなのでしょうか。
── 山口さんはお能の光みたいに動かすといいんじゃないかって言ってくださった。あの頃つき合っていたのは山口さんだけだったの。
── それはいつの展覧会のことですか。
── それは結局、展覧会にしませんでした。しないでお蔵入りにしてしまった。山本さんが「そんな畳みたいな絵が売れるか、ライティングと一緒の絵なんて売れない」とおっしゃって、私は「ああそうですか」って言って、かんかんに怒って、それでみんな実家の物置に送ってしまったんです。
── でも、62年の東京画廊のときは、アンドレ・シェレールが買ってくれて大成功だったわけですよね。
── そこまではいいんですよ。絵だったから。山本さんもわかった。それから、それまで滴の下にあった網の目を絵にした。自分で絵に作っちゃった。ところが、網のなんかは、絵じゃない、描いていない、と思われた。自分では絵のつもりでやっているんだけど、世の中の人は絵とは思わなかった。だから、あの赤い絵なんかがあまり好きではないのは、その時の私の体験が塗り込められているからです。むしろ絵になってしまっている。その時に唯一認めてくれたのが山口さんなの。イタリアから帰ってきたとき、私は一種の失語症みたいになっちゃって、日本語がうまくできなかったんだけど、その時に唯一つき合っていたのが山口さんだった。山口さんも、いわゆる絵じゃないものをねらっていた。
── 66年にアメリカから帰国されて「空間から環境へ」という展覧会に出品されますね。
── 磯崎なんかがやっていたエンヴァイラメントの会の展覧会ね。山口さんも一緒にやっていて、それで私にも声をかけてくれたのね。そのときに、あの三角形の重なり合っている作品を出しました。
── でも、そのころには真鍮のパイプの作品も作り始めていたんですよね。真鍮の作品はアメリカで始めたのですか。
── いや、日本ですよ。東京の下町の金属屋をまわっていて、真鍮のパイプをみつけたのがきっかけね。ただ東京画廊で個展をしたときに、エドワード・フライが来て、グッゲンハイムの展覧会に出すことになって、それでグッゲンハイム賞を貰ったの。エドワードはすごく気に入って、日本に来たとき、毎日のように私のアトリエに来たの。はじめ、中原佑介さんが連れてきてくださった。
── 平面作品における同一の単位の連続と、立体作品になってからの四角や丸いパイプの集積の間には、反復という意味で一貫したコンセプトがあるように思われるわけですが、その上で真鍮への転換を予示するものとして原美術館蔵の絵に貼り込まれた鏡があるともいわれていますね。それから、もうひとつ初期の絵画から気づくことは、厚いマチエールや異質な素材を導入することで二次元の画面の枠を逸脱しようとするような傾向があることですよね。
── やっぱり、立体志向はすごくあったのよね。あの原美術館の絵は、ニューヨークのチェルシー・ホテルで描いたものです。
── なるほど、しずくの繰り返しとか、塗り重ねは、一見、表層で出来ているようでありながら、レリーフのような立体性を出していますね。実際に持ってみるとどの絵も重いですよね。
── 東京画廊の双ちゃん(山本双六氏)が、よく先生の絵は重くてかなわないっていってましたよ。
── 真鍮のパイプの作品に戻ると、これは最初はフレームがなかったというお話ですが、どういう作品だったのでしょう。
── つまり、パイプどうしを接着したり、積んだりしたものです。そういう作品のひとつを、自分のデスクの上において毎日さんざん楽しんでたの。夜明けの光が紫に光ったりね、そういうもので実験していたの。大きな作品の使い残しみたいなのを積んで。ただ、このパイプって、結構、高くて、最初、工場で切り残しを貰ってきたので小さい作品を作っていたのだけど、面白くなってアトリエ中がパイプだらけになって。そうしたらいつのまにか借金もどんどん増えちゃってね。賞なんかもらったりしたら真鍮屋さんが信用してくれて、どんどん材料を送り込んでくれるようになって。それで真鍋さんとか鈴木博之さんとか当時東大の学生でアルバイトに来てくださった建築学科の学生たちがみんなよくやってくれたんです。
── 建築の学生は磯崎さんの紹介ですか。
── いいえ、全然違います。たまたまなにかのイヴェントの会で会ったのね。こういうものの図面を描くとかは、建築の学生だとわけないでしょう。
── 真鍮のパイプの作品については、まわりのかたちが問題じゃない、とおっしゃってますね。大切なのは、パイプの中の光であると。それって先ほどの初期の絵についてのお話にあった「破れ畳」のような下地をそのまま絵として出してしまうという考え方と通じていますよね。「光」というコンセプトを軸にしながら地と図の読み換えというか、虚と実の切り替えというか、ウィットのような軽妙な視点の転換がありますね。
── いつも言ってるように、私にはこうした作品は「作った」っていう気がしなくて、私が「見つけた」んだよっていう感じなのよね。真鍮のパイプは長いので、それを覗いて見るとものすごくきれいなのよね。でも、真鍮屋さんでもそのことは知らないのです。
── その一方で、宮脇さんのお仕事の中には不思議な祈りのような沈潜する作品がありますね。たとえば、60年代の終わりから70年代の始めにかけての《Listen to Your Portrait 》。あれを見ると、ひとつには宮川淳さんがお書きになっていた、鏡の表面の無限の深淵に落ちてゆくという言葉と、もうひとつにはキリスト教美術の「ヴァニタス」や「メメント・モリ」のテーマのようなこの世のはかなさ、無常を語りかけるという伝統が思い浮かぶのですが。
── あれはコンセプチュアルな時期の私の好きな作品です。英語やポーランド語やイタリア語など、いろいろな言葉のものがある。出品する展覧会が開かれるいろいろな国の言葉で作ったんです。あの頃は私はもう人生も長くないと思っていて、年中「死ぬ、死ぬ」って言っていた頃だから、自分の墓石のつもりで作ったの。本当にガンで何回も手術したりして。
── 実際に大変だったんですね。それから、70年代末の《スクロール・ペインティング》ですが、あの作品にはカンヴァスのへりにずっと数字というか日付が入っていますね。
── あのシリーズは一番大きいのがどこかへ行ってしまって見あたらなくなっているんだけど、あれは写経をするような気持ちで描いていたんです。そのころ精神的にちょっと行き詰まっていたのね。
── 同じ行為の繰り返しというのは初期の絵画からつながっていますね。初期の絵について、どこかで、ご自身でもおっしゃってますね、もともと自閉症的なところがあったから、何かを際限なく繰り返すとか、無限に埋めていくとか、という方向に行ったのかも知れないと。
── 最近わりと誰とでも話せる人間になったけど、昔は知らない人と話すことが出来なかったのね。一人っ子だったし、身体も弱かったから。最初のアメリカ留学の頃までは、本当に知らない人と口をきくことが出来なかったけど、そのアメリカ滞在の体験から少しずつ治っていったのかな。
── そういう昔から文学はずいぶんお好きだったようですが。「はじめがあって、終りがあるような物語」には興味がなくなったとお書きになっているのは、具体的にドラマチックなロマンとかを指すのですか。
── そうです。文学でも音楽でもなんでも昔から、大げさな身振りがあるものは好きではありませんでした。音楽でいえば、バッハやモーツァルトはいいけれど、その後のワーグナーなんかは....。文学はそんな物書きになるような才能はないけど、広津和郎先生には、家が近所ですごく可愛がっていただいたから、影響を受けましたね。それこそ、マン・レイに思想的に受けたより、もっとずっと前に広津先生から芸術至上主義みたいな影響は受けてますよ。中島敦の「弟子」とか「李陵」なんかは、大事に何処へ行くんでも持ち歩いていた。あと芥川龍之介の「河童」とか、あのへんね。すごく影響受けているわね。
── さいごにもう一度《うつろひ》の話に戻らせていただきたいのですが、このワイヤーのかたちになって、場に対する関係が一挙に拡大したというか、非常に自由になっていると思うんです。先日、鎌倉の美術館に《うつろひ》を仮設置するのに立ち会わせていただいて、初めて体験したのは、なにもない空間にワイヤーを立ち上げる瞬間に、文字通り虚空に鋭い筆法で線を描くような緊迫感と、そのミニマルな材料による即興的な行為のもたらす大きな解放感でした。
── そうです、おわかりになったでしょう。でも、一筋縄ではいかなくて、いまみたいなかたちで《うつろひ》を作れるようになるには、毎回苦労してきたんです。ワイヤーを支える台の穴のあけ方ひとつとっても、数学的に精密に計算して、はじめは微妙に角度を変えた穴をたくさんあけたりしたんですが、それを実際に使ってみるうちにしぼり込まれて、ようやく今みたいな穴のあいた台になったんです。駒場の東大数学科の新しい建物に《うつろひ》を設置したときには、数学の先生方がすごく関心を持ってくださいました。ですから、酒井忠康さんが、宮脇さんはそんなに《うつろひ》を繰り返してよく飽きないね、と冗談混じりにおっしゃったことがあるけれど、実は一回一回の設置が新たな実験なんです。スタッフといっしょに始めるとき、だれもワイヤーがどのようになっていくのかは、わかっていない。そして、やり始めると、私たちの目の前で、ワイヤーが空間を区切り、なにもないところからなにかが生まれていくのです。
(1998年9月19日、軽井沢、10月8日、東京にて)「宮脇愛子ーある彫刻家の軌跡」展カタログ(神奈川県立近代美術館発行)より転載
Copyright(c) The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama
1)「1962年の秋のパリのある街角で過ごした夕暮れの何時間かが、おぼろげながら、一人の人間にあるつよい影響を与えた…始めがあって、終わりがあるような物語や、大げさなかたちや色にまったく興味を失っていた。そして、はじめもなく終りもないような作品を作り続けていた。」(『季刊現代彫刻』1978年)[宮脇愛子『はじめもなく、終りもない ─ ある彫刻家の軌跡』岩波書店、1991年に再録])
2)MA-Espace/Temps au Japon, 1978, Musee des arts decoratifs, Paris. この展覧会のコンセプトについては磯崎新『見立ての手法 日本的空間の読解』鹿島出版会、1990年を参照されたい。
3)堀内正和、宮脇さんのUTSU-ROHI『いけ花龍生』1980年8月号[宮脇愛子『うつろひ』美術出版社、1986年に再録]
4)「私にとって、かたちをつくることはあくまで主眼ではなく、探し求めてきたものは全く別の所にあった。それは何と言ったらいいか、あらぬものとでも呼ぶべき何か、オスカー・ワイルドのいうすべてのものの背後にあるある隠されたものの精」とでも言うべき何かを、私は常に見ようとしてきたような気がする。タブローやレリーフや立体と素材や手段はさまざまだが、いずれもかたちを作ることが主眼になる限り、このあらぬものは到底確実にとらえることができない。だから私の作っているものは彫刻と言うよりも、むしろ媒体とでもいうべきものかもしれないし、それを見る眼差しが透明や、半透明や、反射や、屈折などをおこしている表相と混じり合うとき、ふっと、なにか別のものが出現する。そんな瞬間を願っているのである。」(宮脇愛子、50歳になって、いよいよ…『美術手帖』1980年6月号[宮脇愛子『はじめもなく、終りもない ─ ある彫刻家の軌跡』岩波書店、1991年に再録])
5)「中国の古銅器の肌を思わせる沈んだ緑の絵の具のマチエール…静かに燃え上がる炎の朱色に染まった画面」。