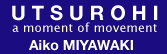 |
|||||
あいさつにかえて
国際的に知られる宮脇愛子さんの、これまでの仕事を回顧する展覧会が当館で開催されるはこびとなったことを、わたしは大変に嬉しく思います。
なぜなら、昨年、宮脇さんは、突然、病に襲われて長期の療養を要するということになり、はたして展覧会ができるかどうかを危ぶまれるような事態もあったからです。幸いにも宮脇さんの強靭な意志によるリハビリテーションの成果で、こんどの展覧会のための水墨画のドローイングを制作されるまでに回復されました。また過日、写真撮影のために車椅子で来館され、自作の《うつろひ》を陣頭指揮で仮設される元気な姿に接することができました。こうした予期しないことが重なっただけに、やはり、感慨深いものがあります。展覧会を企画したのは、実はだいぶ前のことでした。その後、あらゆることに丁寧なこころくばりを示す宮脇さんは、自身の展覧会を充実した内容とすべく、さまざまな角度から検討して工夫をくわえていたように思います。けれども、当初、回顧するということには、いささかの抵抗があったようにもみうけられました。ある意味で、それは当然だったかもしれません。なぜなら頻繁に海外へ赴かれて、そのたびに新しい仕事の成果についての報告を宮脇さんから受けていましたので、近作や新作だけの展示構成にしても十分に魅力的なものとなることは請け合いだったからです。
しかし、宮脇さんの長年月の制作活動と、いまとなっては貴重な記録といっていい、主として現代美術(の“現場”)を媒介とする、世界の、さまざまな芸術家たちとの出会いのなかに結晶した彼女の記憶と経験を、是非、多くの人たち(とりわけ芸術家をこころざす若い人たち)に知ってもらいたい、とする回顧展の方向へと結果的に傾いたのには、それなりの理由があるということをここで申し上げておきたいと思います。パリ・デファンスに完成したグランド・アルシュ(新凱旋門)のかたわらに、宮脇さんの《うつろひ》の大作が設置されたのは、1989年暮のことでした。翌1990年秋には、その完成を記念して、デファンス開発公団によって彼女の個展が開催されました。会場は広さの割に天井が低く(それも考慮にはいっていたのではないかと思いますが)、新作の《うつろひ》のほかにドローイングとマケット、それに20メートルほどのテーブルが用意されて、その上にさまざまなドキュメント、つまり、彼女の過去の展覧会や制作活動を示すカタログやパンフレットの類、それに多彩で人間的な数多くの興味深い人たちとの出会いをものがたる写真資料がところ狭しと展示されたのです。当の宮脇さんにとって、これは「抵抗があったり照れ臭かったり……」というのが、正直な感想だったようですが、しかし、この試みは多くの人たちの関心を引いたユニークな展示となったのです。このときの写真資料の一部に、自伝的な回想をくわえて上梓されたのが、『宮脇愛子−ドキュメント』(美術出版社、1992年)です。
さらに二年ほど前の1996年秋のことでした。35年間、所在の知れなかった初期の絵画作品が偶然にもみつかったのです。余計なものの一切を画面から省いたその作品群は、原美術館で「宮脇愛子 1959−64」展(1996年10−12月)として、はじめて公開されました。「いささかも時の流れに浸食されることのない新鮮さをもって、見る者の眼を奪う」と浅田彰氏はカタログの一文に書いています。まさにその通りで、後年の《うつろひ》の連作を彷彿とさせるものがそこにあると思いました。さまざまな想念を誘発するその画面は、一本の線にも、それまで生きてきた全部がある……と、わたしに語ったことのある宮脇さんの、ほどよい抑制と、限りなく澄んだ知のはたらきが隠されているようにも感じられました。「かれらの群」と題した一文で、宮脇さんはこんなことを書いています。
「いつからはじまって、いつ終るのか、わからない。/わずかにもとの形をとどめるにすぎないこの溶けかかったものたち。かれらの行列は、いつのまにか、少しずつ動きはじめる……」(『はじめもなく終りもない──ある彫刻家の軌跡』岩波書店、1991年)と。この白濁した液体ペルノーの一滴々々がつくり出す果てしない行列の作品が、再発見されたのです。ちょうどこの時期に、宮脇さんはミラノ、パリ、ニューヨークなどに在住し、欧米の現代美術界のなかに身を置いて、生き方の上でも仕事の上でも大きな影響を受けています。しかし、そうしたなかでの、さまざまな経験を集約するその仕方において、宮脇さんは独自であったといっていいと思います。彼女は予見的で実験のこころみにとんだ芸術の思想を受け入れる土壌を密かに耕していたからです。60年代後半から70年代の真鍮やガラスの作品、そして空間を光と運動のなかに視覚化した80年代の《うつろひ》のシリーズへとそれは展開します。そしてこの《うつろひ》のシリーズは、世界の各地に設置されて、いまでは彼女の代名詞ともなっています。まさに宮脇さん自身が歳月を重ねることによって養った美的世界である、と言い換えられるかもしれません。どこか頼りなげなようすにみえるけれども、しかし、構造のしっかりしたところをもっているのは、やはり、彼女の高度な技術と経験がそれを支えているからにちがいないのです。彼女の仕事が初期から今日にいたるまで、一貫した展開の痕を刻み、しかも《うつろひ》に至って確立した世界というのは、20世紀の彫刻史の一隅にあって、爽やかな「例外」として、そのたたずまいは末永く語りつがれることになる、とわたしは信じています。それは旧来の彫刻観では想像もつかなかった、ある種の軽やかで透明なる美的世界の「出現」だったからでもあります。とにかく、こんどの展覧会に再発見された初期の絵画作品をくわえることができたという幸運が重なって、回顧展への期待はさらに膨らむことになりました。しかし、単なる「過去との再会」というかたちでなく(宮脇さんは厳しく過去との決別を意図していたかもしれませんが)、こんどの展覧会は、自身の新なる「創造への出発」とするという考えにおいて、いかにも彼女らしい爽やかな心意気を感じさせるようすのうちに、準備は進行していたのです。ところが、上にも記したように、宮脇さんは病に倒れ、一時は中断することもあるのではないか、と心配するほどだったのですが、何とか展覧会に漕ぎ着けることができました。これは一にも二にも宮脇さんの信念の賜物だ、とわたしは思っています。
いつの場合にも宮脇愛子という作家は、その仕事の原点にもどる勇気のある人だということを痛感させられました。その意味で、こんどの彼女の水墨画による新作のドローイングには大いに期するものを感じます。また展覧会のすべてにわたって気を配る、彼女の神経の細やかさと靭さにも、わたしは感服しました(これは無理をなさらないでいただきたい、という思いとも一緒ですが……)。いずれにせよ、こんどの展覧会を通して、宮脇愛子という作家の40年におよぶ仕事の跡を追いながら、彼女の創造活動の地平の見晴らしのよさを印象づけられる鑑賞者が、一人でも多く生まれてくれることをわたしは期待しています。最後になりましたが、展覧会のために貴重な作品を貸していただいた美術館、画廊、所蔵家の方々、また多大なご協力をいただいた関係各位に、深く感謝の意を表します。企画の段階から当館の厄介なお願いに、一から十までこころよく応えて下さった宮脇愛子さんと、超多忙ななかでしばしばご相談に預かった磯崎新氏にお礼申し上げます。また、本展カタログのために一文をお寄せ下さった北杜夫氏、辻邦生氏、論考を頂戴した林道郎氏、ケート・リンカー氏にこの場を借りてお礼申し上げます。さらに、宮脇さんとは長いおつきあいをもった東京画廊の山本双六氏、宮脇さんと絶妙なコンビで四半世紀にわたって彼女の作品を撮影してきた安斎重男氏、そして複雑な展覧会の業務の多くを担ってくれた当館学芸員太田泰人氏、ならびに宮脇アトリエのスタッフ(松下、杣木、松田の各氏)にもあらためて、ここでありがとうをいいたい。
1998年10月
「宮脇愛子ーある彫刻家の軌跡」展カタログ(神奈川県立近代美術館発行)より転載
Copyright(c) The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama