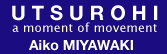 |
|||||
カリグラフィの線のように
常識的には空間は一組の直線によって決定されることになっているが、それは宮脇愛子の作品によって論破される。「うつろひ」となづけられた彼女の彫刻作品では、ほそいフィラメントが、ひとつではなく複数の空間を形成し、共鳴しあう両義的な領域という多様性を提示し、わたしたちの認識の日常性を置換する。明解であると同時にミステリアスな修 辞や、非物質的な概念を示唆する言 辞を用いながら、宮脇は透明性のあるネットワークによって虚空を捕捉する。彼女の彫刻は空間をつつみこむのではなく、かそけき輪郭線のなかに共鳴しあう無限の空間をあきらかにする。
《うつろひ》は“a moment of movement” をコンセプトとしているが、それは宮脇が1979年から制作している一連の作品群の名称でもある。当初からシリーズとして意図されているので、《うつろひ》の作品群は厳格とまでいえるほど限定的なヴォキャブラリによって構成されるという共通性をもっている。それぞれの場合で、細いステンレス・スチールのワイヤが、低い台座あるいは柱などの形状をもった、支持体の間に架構され、それぞれのワイヤは支持体内部に固定される。支持体はさまざまなのでそれぞれ異なったムードが醸しだされる。たとえば、バルセロナ・オリンピック・スタジアム(バルセロナ、1990年)前の広場では風のふきすさぶ平原に整列した群衆を想起させるし、デファンス地区(パリ、1989年) では深い森の木々を連想させる。他の多くの場合では、支持体はほとんど目にとまらないので、作品は宙に舞うカリグラフィの線のような印象を与える。ワイヤの太さ、長さ、本数は作品によって異なるが、ワイヤによる円弧は支持体によって厳密に境界を定められながら、空間にかけわたされて、空間を複雑化するので、その円弧状の輪をえがくときにつくられる関係性によって特徴づけられる。この関係性は、支持体の位置、ワイヤの長さ、荷重などの差異を前提とする数学的な計算によって決定されるものではあるが、さらに自然によってもたらされる効果も調合される。風はステンレスの円弧をそよがせ、きしませ、その形を変化させ、金属と空との微妙な構成のなかに多様な空間をあきらかにする。おなじように、自然光は場所と時間によって変化して金属の反射面にきらめきを投げかける。この発光性には外部の光の反射と屈折という二重の原因があるが、複数の線の共鳴する光は空間内の微細な変位に対応して対位法的なリズムを生じる。それぞれの変化はつねにかたちを変えつづける構造体に何千回もこだまして、ワイヤをしっかりと保持する台座の安定性に抗いつづける。
ある敷地に恒久的に設置されながら、根源的な非恒久性(インパーマネンス)を指向する作品を制作するにあたって、宮脇は日本固有の「うつろひ」という概念の中核をなすパラドックスを援用する。
“a moment of movement”と英訳されるこの概念は、変化が世界内に永続的に存在することを示唆するが、その変化はほとんど知覚不可能で非実体的なかたちとしてのみ感知される。それを大江健三郎は「持続する“うつろひ”の、永遠でかつ一瞬の輝き」1) と表現し、その多義性に言及している。すなわち、変化はすべての生にいのちをもたらす目にみえない常数として虚の中に刻印されている。したがって、「うつろひ」は生の無数の断絶性の中に存在する連続体であり、数かぎりない異質のできごとを時の果てしない織物へと変換する流体のリズムである。それは、可視的というよりは不可視的であり、実在するものとして認識されるものというより「知覚可能な」ものである。それは、世界の立証可能な構造体の中にひそやかに共存するものとしてのみ明示される。そのために、「うつろひ」は自然現象の中では、四季のうつりかわりや光と影の微妙なたわむれとしてつかのま捕捉されるにすぎない。あるいは、哲学者の投げ入れた小石が静かな水面に生じる波紋のように、芸術家である宮脇が彼女の作品を通じてわたしたちの視覚の場になげかける明確な平衡状態として。
《うつろひ》シリーズによって、このような持続するはかなさという感覚を「描写」し、「表現」するのが宮脇の主眼ではない。作品との邂逅に際して、見るものの知覚の地平にそういった感覚を生成し、喚起することが作家の狙いである。この邂逅は可視的な世界の地平に生じるもので、曲線によって分節され構築された空間という、壊れやすい迷宮の中を、宮脇のいうところの「対象と視覚との間」2)に間接的に出現する、目にみえないものをさがしもとめながら、曲折する線形のうつりかわるありさまを凝視するものにのみもたらされる。ところで、この思考を喚起するフォルムの源泉は何で、それはどのようにして生まれたのだろうか?
宮脇は、彼女の母国である日本以外でも多くの文学や哲学の風土の中で暮らしたことのある、きわめて洗練された芸術家である。それにもかかわらず、彼女が《うつろひ》シリーズの原点を、芸術運動でも、美学的な概念でもなく、病弱な子供の自由な線へのあこがれという個人的な記憶にもとめているのは興味深いところである。この夢は若き日の宮脇自身がその主人公であったのだが、病床という凍結静止状態と拘束されない運動、制限状況・閉鎖状態と大空の無限の開放性という二項対立をもたらす。そしてその夢の中で、線は矢のような速さで空を切り裂き、その存在を刻みこむ。とはいえ、この夢は彫刻のメタフォアでもある。彫刻がかたいフォルムと重量感のある素材に伝統的にとらわれていたことと明瞭な非物質性をもった線とが対比されている。彼女の作品の出自だけではなく、時代に拘束された彫刻の伝統を作品を通じて否定することに触れながら、「開放され、軽やかな、動くものがほしかったのです。」3)と宮脇はあるインタビューの中で語っている。
宮脇は彼女の作品は彫刻というよりは「媒体」的なものであるというが、実際、彼女の初期の作品は彫刻の伝統にしたがうものでは全くなかった。彼女は画家として出発し、日本の大学教育を受けたあとでミラノとパリを訪れた。1960年代初頭の彼女の最初の展覧会は欧州のいくつかの画廊のきわめてインターナショナルな文脈の中でおこなわれた。ヨーロッパで彼女はマン・レイやその他のシュールレアリストたちと出会うことになるが、彼女の興味はシュールレアリズムの絵画の技法にではなく、むしろその理念にあった。実体的なオブジェではなく「概念の物質化」としてのアートという宮脇の関心がこの頃に端を発するものであることは想像に難くない。60年代および70年代の初期において、当時の美術の関心がもっぱらマチエールにあったときにも、宮脇は光のゆらめきをキャンバス全面に形象することに専念していた。モノクロームのレリーフの作品のシリーズの中で反復されるかたちは重層する列状のパターンをなしているが、表面に繊細な起伏を生じるように大理石粉を混合した絵具が用いられている。その結果としてたちあらわれる光は実体的であると同時に形而上学的な意味で使われている。すなわち、宮脇による魔法がキャンバスの表面に奇跡を生じ、作品全体に意味をあたえ、照らしだし、啓蒙をもたらす。60年代末に宮脇は彫刻に転じ、真鍮のパイプを集積した中に開かれた窓のような開口部をもったアッサンブラージュを制作した。さまざまな開口部によって生みだされる光の戯れが作品の中核をなしているが、それは1970年に開始されたMEGUシリーズにも共通するところで、そこでは光が厚く重いガラスの緑の堆積を通過することにより、あたかも「硬質の海」の中にとらえられたかのように変換される。しかし、真鍮もガラスも重量感のある素材である。軽やかで、自由で、可動性をもつという必要条件を満足する彫刻的な手段に宮脇が到達するのは70年代の末まで待たなくてはならない。
絵画から彫刻への移行期間の間も宮脇はドローイングを制作し続けた。当時のドローイングには、マラルメさながら、アーティストがページの余白から空間を出現させるかのように、コンテを用いて、曲がりくねった、カリグラフィのような線がまばらに描かれている。紙の白い表面は、西欧の弁証法がいうような、アーティストが創造するためのニュートラルな支持体ではなく、ひとつの「空白」であり、源であり、場であって、そこからかたちが生みだされると考えられている。空間はからっぽなのではなく虚(うつ)であり「無が(すなわち全てが)充満している」。したがって、この空間の中や空間から生じるかたちは形態を変換する場と重層的な関係にある。マラルメが東洋に魅せられ、虚による生成を暗示したように、宮脇も中国の「気」の思想から影響を受けた。「気」とは宇宙に内在する目に見えない存在であり、すべての有機体の源であり生命をあたえるものである。光の場と空間を誘発する線とを彫刻という媒体に置き換えるという独創的な作業、それが1979年に始まる《うつろひ》のシリーズである。
《うつろひ》シリーズのプロトタイプとよべる作品模型は東京画廊で1979年に開かれたあるグループ展に展示されたが、一連の野外作品としては1980年の名古屋が最初である。こういった初期の作品では、彫刻の形態は光を反射するワイヤによるミニマルなかたちに還元される。その結果として、空間の領域が拡張し、拡大されて、フォルムの字義通りの「周囲」だけでなく、フォルムが現出し、不断に変形し、交差し、増殖する内部領域までもとりこむことになる。しかし、宮脇がジュヌビエブ・モニエに語ったところによると、初期の作品の製作は「困難の上、ワイヤも現在のものほどフレキシブルではありませんでした」。したがって、「ワイヤのフレキシビリティは作品模型では達成できましたが、実作では達成できませんでした」4)。コンセプトをより的確に表象するための素材と手段を発見しようというたゆみない努力には、宮脇のすべての作品に共通する、技術上の進歩とクリエーティブな想像力との対話がいかんなく示されている。最終的に、彼女は吊り構造の橋梁に用いられるテンション加工されたステンレス・スチールのワイヤに到達した。ワイヤの曲率などの設定を保持し、また決定づけるベース(彫刻の「台座」をコンセプチュアルであると同時に洗練された形で置き換えたもの)に関しても宮脇はねばり強く改良を続け、今日では作品の特徴の一部となっている基部(ベース)の形状にたどりついた。このベースにはケーブルを異なった角度や異なった位置にアンカーできるようにいくつもの穴が穿たれ、さまざまなテンションやカーブを可能にしている。敷地に応じて、ベースの数、寸法、素材は変えることができるが、それは彫刻の歴史のなかでも他に類を見ないものである。
1980年以来《うつろひ》は、テキサスにある森の中のプライベートな彫刻庭園(1985年)からリヨンの公共集合住宅の広場(1985年)まで、また日本国内のいくつかの著名な美術館や公共の建物の内部や野外といった、さまざまの国や土地に設置された。サイト・スペシフィックな要求に答えて、それぞれの作品はそれぞれの設置場所の細かな差異に呼応し、その結果、張力ワイヤとベースという簡明な語彙からは想像することのできえない、多様な形状と雰囲気をもたらした。テキサスの場合を例にあげるなら、浅い池の土手の草むらにベースが埋め込まれているので、ワイヤは細い葦の茎のように宙にさまよって見える。他の作品(奈義町現代美術館、1994年、群馬県立近代美術館、1994年)ではベースを池の水中に直接沈めてしまうことによってこの効果は強化される。これらの場合では、光の屈折に水面で反射する像が重合して、こだましあう金属のトレサリー(窓格子模様)が出現する。箱根の彫刻の森美術館(神奈川県、1981年)と琵琶湖大橋彫刻プラザ(滋賀県、1982年)では、広々とした緑の遊歩道を低い位置でまばらに弧が横断して緑の芝生と野外空間の広がりを強調する。また、パリのデファンス地区(1989年)はそびえ立つ現代建築群の間に舗装された広場がちりばめられた都市空間だが、そこに宮脇は背の高いネオパリエ(結晶化ガラス)の円柱を非対称に配置した。その頂部は鏡面仕上げのステンレス・スチールでカバーされ、無数のたゆたう曲線の連続体を保持している。こういった、彫刻の形態上の装備は、おのおのの場合で考案され、反復されることのないものだが、そこに気候によってもたらされる変化が付加される。ワイヤは雪の荷重を受けると振動しながらたわんでいくように見えるし、ゆらめく光の中ではふるえる蜘蛛の糸のように変容する。見るものの視角は彼あるいは彼女がパラメーターを探りながら彫刻のまわりを歩くにつれて構築されるが、それによって、作品内部に構築されている絶え間なくうつりかわる空間構成だけでなく、周囲の風景にも新たな視点をもたらすことになる。なぜなら、宮脇の彫刻は、見る者がそれをある一定の時間(彫刻というメディアの従来的なロジックに従うなら「あらゆる角度から」)経験することだけでなく、一連の事象が作品自体の内部変化によって変化するものとして経験することをも要求するからである。線が相互貫入し、たがいに屈折しあい、かたちの不断の消失と再生を繰り返すうちに、それぞれの空間はもうひとつの空間に順応し、それぞれの風景はもうひとつの風景と融合する。
宮脇の「持続するはかなさ」の静かなささやきは近年日本で実現されたふたつの常設展示作品に雄弁なほど集められた。ひとつは群馬県立近代美術館の前面の四角い水面に設置されているが、そこでは三組のポールが、注意深く対称形を避けながら水中に配置され、水上および空中に優雅に扇状の弧を描くワイヤの放射を支持している。ワイヤは光の変化にきわめて敏感に反応し、光の位置によってはその厚みを増し、また場合によってはか細く震えているようにみえる。そのさりげない変容は作品の周囲の環境の変化をとらえ、そのため、見るものたちは、通常いくつかの群をなして、震えながらきらめき輝くステンレス・ワイヤに現出する、酷薄な光のカデンツァの前でたちつくすことになる。こういった印象は、安定していてフラットで均一的な正午の光の下か、または、バラ色やオレンジ色の色相が大空に広がり、ループ状のワイヤにそのパターンが反射される日没時にもっとも鮮明になる。
奈義町に最近完成した現代美術館の中の作品は異なった印象をもたらす。光と影の複数の瞬間は、リフレクティング・プールの魅惑的な輝きをもった、水面の上を浮遊する屋外の作品と、建築家磯崎新がこの作品のために設計した、大きな、薄暗い、半闇の空間のそこかしこにこころもとないばかりに配された、室内の作品との対比関係に集約される。しかも、この対立は連続性をもったプロセス ── 変化のシークエンス ── の中のふたつの幕間劇として示されている。このプロセスは、建築家によって設定された大きなガラス面が暫定的に室内と屋外の作品を区分しているように、ふたつの作品を関連づけ、融合する。屋外では、水面下に敷きつめられた黒い石が細いワイヤを支えている。ワイヤは張力構造をあたえられた花束のように水面から立ち上がり、石の冷たい領域にやがて帰還する。この細径に沿って宮脇の審美的な回路設計がなされているが、そこには光の回路だけでなく風の回路も含まれているので、彫刻は環境の微細な変化に忠実に反応する。室内では屋外とよく似た石が地表を被い、人工照明によって照らしだされあるいは影をつけられた中で、屋外に匹敵する静謐さが達成されているが、彫刻のワイヤによる格子模様は、見るもののささやきや動きに逐一反応して、あたかもさらさらときぬずれの音をたてているかのようだ。宮脇はこの作品について、「奈義の水と地に関係づける」ことを意図したと書いている。水と地によってかたちづくられた座標系の上に、ほとんど知覚不可能なムーブメントからなる一大絵巻を宮脇は描きあげた。
こういった微妙な運動は、目にみえないリズムの可視的な言明ということができる。それは知覚では必ずしも把握できるものではなく、視覚と感覚のエッジで、直観によるものとしてかろうじてとらえられる。これこそ「対象と視覚との間」に間接的に現出する目にみえないものについて語ったときに、宮脇の言わんとしたところではないだろうか。ところで、彼女のアプローチはもうひとつの異なる次元をも示唆している。近年、西欧の哲学者が、西欧の歴史の中でながく受け継がれてきたトンネル型の視覚体系──遠近法という頑強なものの見方に根ざしているのだが──を是正しようとする中で、日本思想に関心を示している5)。トンネル型の視覚体系の中では、視覚には固定された「カット(場面)」か知覚上の「フレーム(枠)」のどちらかが与えられるにすぎない。こういった静的な視覚体験に対して、根源的な非恒久性をもった全体的な場の中では、視覚のインスクリプション(刻みこみ)がおこなわれる。なぜなら私たちがある対象について見るものは、その対象の周囲であらゆる方向に拡張している、それ以外の残余の宇宙すべての中の、たったひとつの像でしかないことがすでに明らかになっているからだ。この変容しつづける場──見えないし、見ることもできないが、視覚には不可欠のもの──こそ「空白」や「空隙」といった、私たちの視覚の周囲にあって視覚に影響を与える不可視性の外被を構成するものである。そしてこの不安定な場は《うつろひ》の相補的な相互作用の中でかたちを変えていく。単に、あるひとつの瞬間のムーブメントなのではなく、無限に続くほとんど識別不可能な変化の複数の瞬間。《うつろひ》の彫刻を根源的な非恒久性をもった場と可視性の前提条件でもあるはかなさという目にみえないものから分離することは不可能である。
すでに述べたように、宮脇の芸術は世界を旅したものの営為であり、ゆたかに同化された幅広い、審美的で、文化的な経験を反映している。それにもかかわらず、それは日本の風景にその因をおくものである。しかし、それは実体的な「事実」としてではなく、形而上学的な啓示として理解されなくてはならない。なぜなら日本の風景の特徴は同一性と反復性にあるからで、山野や沼沢地は列車や車の窓の外をつぎつぎに流れ去っていくが、そのほとんどは何の変哲もないものだし、重要でもない。美しい山や森や谷は偶発的な出来事であり、複=複製されたフォルムが連続する中で噴火に遭遇するようなものであって、経験全体に意味をあたえるものだ。美は地平に突如として現出する。すなわち、ある意味ではそれは関係性という機能に他ならない。美は、反復性という構造の中に、反復性という構造を通じて生みだされるものであり、その構造から逃避し、また同時にそれを変容するものでもある。この出来事は、つかのまのとか偶発的なといった性質を帯びているので、美との出会いの瞬間には稀少価値とはかなさとが同居する。宮脇が反復する線と永遠にかたちを変えつづけるフォルムとによって構築するのは、このような、つかのまの、非実体的な、しかしそれにもかかわらずリアルな、現出に他ならない。
(訳:渡辺真理)
「宮脇愛子ーある彫刻家の軌跡」展カタログ(神奈川県立近代美術館発行)より転載
Copyright(c) The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama
1)大江健三郎「うつろひ STORY」、『うつろひ』
美術出版社, 1986, p.73
2)ラッシェル・ステラとのインタヴューからの引用による。 The Journal of Art vol.2 no.3, December 1989, p.5
3)ジュヌビエーブ・モニエとの1990年1月27日のインタビューによる。
“Utsurohi,” in Aiko Miyawaki: Utsuroi (exhibition catalogue). Flammarion/ Art Defense/ Baudoin Lebon, 1990, p.36
4)同上
“Aiko Miyawaki,” in L’Art et La Ville. Geneva: Skira. 1990, p.136
5)私はここで視覚についての、西欧哲学者側からの日本の思想家西田幾太郎とその弟子、西谷啓治の著作への関心について言及している。この件についての著名な美術史家による討論は Norman Bryson, “The Gaze in the Expanded Field” in Hal Foster, ed. Vision and Visuality. Seattle : Bay Press. 1988, pp.87-108. を参照のこと。