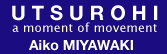 |
|||||
あなたの肖像にききなさい
あらぬもの
宮脇愛子の仕事を追ってみてゆくと、様々にその現れが変化する。形式の問題としても、素材の問題としても。それに対して、宮脇自身のこういう言葉がある。
「しつこいくらいに一生貫き通す自分の思想がなければ、アーティストとは言えないでしょうね」。
たしかに、宮脇の仕事の変化はつねに何か一つのことと緊迫した関係にある。わたしは、ずっとそういう印象を持ちながら、これまでそれをまじめに考えることをしなかった。その間隙に彼女自身の言葉が落ちてきて、「一生を貫き通す思想」について、もう少し腰を据えて考えてみないかとわたしをいざなう。
一つのこととはなんだろうか。宮脇自身は、別のところでそれを「あらぬもの」と表現している。簡潔かつ深いその言葉は、実際に作品を生み出しつづけている作家にして説得力をもつ表現の経済学である。受けとめる側のわたしは、その「あらぬもの」を、やはり、いったん言葉の不純の中にひきおろして考えてみたいと思う。でなければ、「あらぬもの」は、美しい響きをもった惹句として、あいまいなまま消費されて終わるのではないだろうか。
宮脇愛子の仕事の意味を考えようとするとき、二つのむずかしさがあると思う。
一つは、彼女の歴史における位置づけの問題である。ある作家の仕事の意味を考えるとき、多くの場合、批評家なり研究家は、その作家が属していた文化圏、美学上や政治上のコミュニティー、あるいはもっとゆるやかな趣味の共有といったコンテクストを手がかりに、そこから作家の位置を測定しようとする。そういう方法をとることは、宮脇の場合むずかしい。というのも、彼女は、作家として本格的に活動をはじめる前から海外に出、最初の個展こそ東京だが、その後すぐミラノ、ローマ、パリ、ニューヨーク、その合間に日本と、多拠点において作家活動を開始したからである。その彼女の多拠点性は、限定されたコンテクストとの関係において彼女の仕事を測るという目論見を初手から破綻させる。「ミニマリズム」や「コンセプチュアリズム」という「イズム」の問題としてもそうだし、「日本と西洋」という問題設定にも彼女の仕事はおさまりきらない。しかし、そうは言っても、彼女の仕事は孤絶しているわけではなく、それぞれの土地における出会いを通じて、同時代の美術の多様な実践とたしかな接点をもっている。ただこの接点は、単なる影響という形ではなく、応答的かつ多層的で、それを対象化することはとてもむずかしい。
この自明なコンテクストの不在は、その結果として、もう一つのむずかしさを招く。むずかしさと言うより誘惑と言うべきかもしれないが、特定の関係性の中に宮脇の仕事を位置づけることの困難が、過剰に主観的で詩的な言説の方へと論者を向かわせる、そういうことがあるように思う。事実、これまで彼女の仕事について書かれてきた論は、詩的な装いにおいて美しいが、同時に、どこか、言葉が上滑りしているという印象を与えるものが少なくない。「あらぬもの」の現れにより添い、その経験に対して言葉によって道をつけてゆくというよりは、性急に詩的なレトリックで蓋をしてしまう、とでも言おうか。
この二つのむずかしさは背中あわせである。その間を縫って何がしか意味のあることを言おうと思えば、迂遠かもしれないが、やはり宮脇の仕事に身を寄せながらゆっくり考えてゆくことである。そこからはじめることでしか、「あらぬもの」の影を──たとえそれが不完全なものだろうとも──捉えることはできないだろう。「詩的」の速度に抗って、作品との対話を引きのばし反芻することである。わたしは以下に、短いながらいくつかの概念を手がかりにそういう作業をしてみたいと思う。そういう過程の中で、様々に交錯する歴史のコンテクストとの応答関係も、副奏的な下旋律として遠く鳴り出すにちがいない。
光/痕跡
素朴な観察からはじめよう。
宮脇の仕事を一つの連続として見たとき、様々に現れを変えながら一貫していることの一つは、彼女の光に対する関心である。
たとえば、1960年前後の《WORK》というタイトルのついた平面の連作。これは、大理石の粉を混ぜた絵具を使って、鳥を思わせる微妙なレリーフ状のパターンを、平面上に、差異を伴いながら反復した作品群だが、これを展示する時に山口勝弘は、光によって現れが変わるので、ゆっくり動くライトを使ってはどうかという提案をしたという1)。そのアイディアは、結局画商によって「けられ」、実現にまでいたらなかったが、山口の恣意的な思いつきというより、間違いなく《WORK》の作品群そのものに根ざしたのものと思える。表面からかすかに浮き上がり、微妙な光と陰の交錯を見せる石の混ざった絵具のレリーフ。照明や見る者の位置の変化に応じて刻々違った姿を見せる作品は、たしかに、そんな試みをうながす構造をもっている。
この微妙な起伏をもつ表面と、それを包む光に対する深い関心は、やはり60年前後にモノクロームの絵画を制作していたアグネス・マーティンやロバート・ライマンの作品を思わせるところがある。が、彼らにおいて顕著な筆触そのものに対する関心よりも、宮脇において特徴的なのは、「石」の粉を含む絵具をパレット・ナイフを使って画面にのせてゆく、もしくは刻印してゆく、その彫塑的な感覚である。そこに、柔らかい光の振動と硬質な物としての表面の共存が出現するが、この組み合わせは、宮脇のその後の仕事を通じて、様々なヴァリエーションとして追求されることになる。
事実、60年代半ばから後半にかけての真鍮のパイプによる立体の作品群は、《WORK》にすでに暗示されている彫刻的な空間の新たな展開と見ることができるし、ここでも核心の問題は、真鍮という硬質の素材と、それを包み振動する柔らかな光である。その展開は、作品としても、1964年に制作された《無題》を折り目にして連続している。この作品の中央に置かれた正方形の鏡は、立方体のやはり鏡のような表面を持つ真鍮による作品群を予告しているといっていい。
しかし、そういう連続がある一方、真鍮の作品群において光と素材の関係は、《WORK》には見られなかった緊張を孕むことにもなった。これは、真鍮という素材の性質によるところが大きいが、同時に、宮脇自身がパイプを微妙にずらして置く、その方法によっても加速され、時には緊張が分裂にも近づく。つまり、多方向にうつろう光が、堅固な金属の形や枠を裏切り解体するような印象をまで現出するのである。作品の基本構造が、多く、整然とした幾何学的な形態によっていることも、イデアルな形と現象としての光の自己解体的な共存をいっそう前景化することともなっている。思うに、この物質と形と光のせめぎあいは、宮脇を思わぬ深みへと引き込んでいったのではないだろうか。わたしの印象では、この真鍮の時代が、もっとも多方向的に、しかも多量に宮脇が作品を制作した時代ではないかと思うが、時には散漫に広がりもしたその過剰さこそ、宮脇が光の実験へと一歩深く踏み込んだ様相をよく伝えていると思う。
したがって、彼女が、真鍮ののちガラスという素材を発見したのは納得のゆく道筋で、その《MEGU》というタイトルのついた作品群において、硬質な素材と光のせめぎあいは、素材そのものに内在するものとして一層ラディカルに追求されている。ここでもやはり、幾何学的に積み上げられたガラス板の堅固とした秩序を光は裏切り、溶かし、幻像へと還元してしまう。
ところで、《MEGU》という一見不可解なタイトルは、宮脇によれば、岡山弁で「割る」を意味する「めぐ」という言葉に由来するらしいが、この「割る」という作業が作品の制作過程に取り入れられたことには、新しい展開が見えている。実際には、宮脇自身が言っているように、ガラス板をゴシゴシと切ると断面が透明にならないという理由から、「割る」必要が生じたのだろうが、結果として、瞬間的な力の負荷の痕跡を作品に導入したことは、作品自体を力線の交錯する場に変容させることになった。《MEGU》の幾つかの作品では、断面だけではなくガラスの内部にも穴があけられているが、この内部に穿たれた力の痕跡は、ガラス内部の虚空にたゆたいながら、外側の断面に残る力の痕跡を照らしかえす。
「痕跡」というふうに捉えると、これは、絵具を平面上に置いてゆく初期の《WORK》の手の動きの痕跡、あるいは真鍮の作品のパイプを一つ一つずらしてゆく手の動きの痕跡とひとつながりとも見える。しかし《MEGU》においてその痕跡は、「割る」という一瞬の繊細な暴力に凝集している。ガラス板の断面にかすかに残された割る力の生々しい痕跡は、それに行き当たった視線を、「ピシッ」という破断の音によって撃つ。作品のみかけの静けさの芯から、すっと切っ先が伸びてくる。
虚
「割れ」が作品にもちこむ事件性は、同時期の他の仕事にも生かされている。たとえば、1977年に制作された黒の花崗岩による、やはり《MEGU》と題された作品。これはきれいな三角柱を真ん中から割り、三つの破片へと分裂させた作品だが、ここにおいては、割れが作品の内部に生じているために、かつては一体だった断面の間に生じる空間が、作品の結界の内部にありながら作品そのものではないという矛盾した性格を持たされている。この「虚」の空間に対する宮脇の関心は、光への関心と平行して宮脇の仕事に一貫しているが──《WORK》の絵具の谷間、真鍮のパイプの空洞、ガラスの透明な虚空──、この花崗岩の《MEGU》において一層、鮮明な形でそれが問題化されている。
「割れ」という事件から生じる虚の空間。同じ問題意識は、さらに、ほぼ同時代の《STUDY OF HOMOLOGY》という連作にも共有されている。ただ、こちらは、整然とした真鍮の作品による幾何学的な切り込み ──あるいは形どうしの相互貫入──としてとらえなおされているので、むしろ、「割れ」と「虚」に対する方法的な反省と言った趣がある。一つの立方体が、鋭い切り込みによって二つの形体に分離する。みかけは随分異なるその二つの形体が、組み合わせてみると当然のことだが一つのきれいな立方体を成す。重要なのは、見る者がそれをプロセスとして感じられるようになっていることで、実から虚が生まれ、虚から実に帰る、そのプロセスを意識的に見せているところにこの連作の意義がある。時間性の導入と言おうか。痕跡を生じさせるメカニズムそのものを作品の中に対象化している。
「痕跡」とは、ところで、何だろうか。わたしは、物理的な力──それは光であったり、外部から加えられる衝撃であったりするのだが──を受けとめる物質としての作品の問題として「痕跡」ということを言ったのだが、これを時間論の立場から考えると、過去と現在の不可思議な共存ということになるだろう。
チャールズ・パースという記号学者は記号を3種類に分類したときに、足跡など物どうしの物理的な接触や関係が生じた時に残される痕跡を「インデックス」というカテゴリーにまとめた。その時彼は、他の二つの種類の記号(シンボルとイコン)とインデックスを分かつ本質的な違いを、後者が内包する「現在性」あるいは「同時性」に見ている2)。たとえば、「あっ」と言って人が飛ぶ鳥を指さす。この時の指と鳥の関係はインデックスなのだが、これは、その瞬間の「現在」にしか発生しない記号関係である。同じように、足跡などの痕跡も、ある瞬間、たしかにそこに物どうしのコンタクトがあったという同時性の結果生じる記号である。だから、インデックスは、現在性の記号だと考えられるのだが、それは、あくまでも記号の「生産」の観点からである。問題を複雑にしているのは、その痕跡を後から発見し、何かの存在の記号と解釈する受けての側から見た時に、痕跡は、非常に不思議な「過去の中における現在」という感覚を喚起することである。あるいは過去(の出来事)が現在のまっただなかにたちあがるとでも言おうか。
写真
わたしが、先に《MEGU》の見かけの静けさから切っ先が伸びてくると言ったのは、このことにかかわっているが(過去に起こったはずの「割れ」が現在のただなかにたちあがる)、そのインデックスという記号の不思議な喚起力(盲目的な強制力)を典型として担っているのは、実は写真という媒体である。パースの論をうけたロザリンド・クラウス、そしてパースとは別の地点からやはり写真のもつ強烈な喚起力について考えたロラン・バルト、こういった論者たちが出発点として共有しているのは、写真を見るという体験が、時に、過去が現在として見る者を不意撃つ、その経験のなまなましさである3)。そして、この痕跡と写真の、インデックスという概念を介しての連続は、わたしに一つの解釈の窓を開いてくれる。というのも、わたしは、かねてから、宮脇愛子にとって写真とは何かという問題に、浅からずとらわれていて、彼女が日常の出会いをも含めて自らの活動の軌跡を写真というメディアによって逐一残してゆくその行為を、彼女の作品との関係においてどう考えたらよいかという疑問を抱えていたからである。
もちろん、彼女が創造した作品と、彼女が写った写真を同列に論じることはできない。しかし、何と言うか、その両者は、同じ、こう言ってよければ、絶えざる現在としての生を刻印しようとする欲望に貫かれている。ただその刻印は、刻印されたものであるかぎりにおいて、すでに死となった現在の跡にすぎない。しかし、刻印の瞬間に生じた物理的なコンタクトの痕跡は、その死の中に鋭い現在性を息づかせている。生の中に死が、死の中に生が息づく場としてのインデックス。それこそ、宮脇の作品と写真をつなぐ蝶番なのではないだろうか。その意味で、《MEGU》と平行して宮脇が、巻物状の長い紙面に網の目のパターンを描きつないでゆく試みをしていることは示唆的である。その網目は、一つ一つを見れば、過去と未来の両方から切断された(物語をもたない)現在であり、描き終わるとともに死んでゆく。しかし、と同時に、その無限に続く屍の累々は、今、網の先に描き加えられている新しい一つの網目=現在によって反復され生きなおされている。《MEGU》、《WORK》、パイプの作品においても、一つ一つ別のものとしてあるユニットを積み重ねてゆくという方法は基本的に同じで、それは写真をとり、とられという行為を日常として反復していることとどこかでやはりつながっている。
そして何よりも、痕跡と写真、その両者を可能にするための媒体として「光」がある。宮脇の作品を見る経験の中で、見る者に、たえず変化する「現在性」の感覚を喚起するのは何よりもまず光の現れであった。その同じ光は、写真が世界と「現在」においてコンタクトする物理的な媒体でもある。写真は、光による印画紙への世界の焼き付け=刻印であり、それは、光に包まれ光を発する宮脇の作品が、刻々と変容し、つねに「いま、ここ」の反映としてあることに呼応している。
音/振動
さて、インデックスの経験の現在性ということで宮脇の作品をもう一度見なおせば、わたしには、光、負荷される力の痕跡、そういった要素に付随しながらもう一つ、宮脇の仕事に厚みを与えている層があると思う。それは、先にも触れたが、音の感覚である。音と言っても、実際にそれが聴こえてくるわけではなく、「振動」と言った方がいいのかもしれないが、作品から発せられる無音の振動が見る者の身体を包むという感覚がある。これは、真鍮のパイプの作品において初めて意識されたものだろう。様々な楽器の構造とパイプの類似が、そんな振動の感覚を否応なく喚起するが、その言わば隠喩的な相似が、《MEGU》において、鋭い「割れ」の音として作品の素材そのものに内在するようになる。
この無音の音の感覚は、やはり深く作品経験の現在に密着している。見る我々の身体と作品が、一つの共鳴を起こすという感覚。それは、多くのミニマリズムの彫刻において、身体の問題がもっぱら視覚と触覚を軸に展開することと宮脇の仕事が一線を画する部分である。宮脇は、文字通り「振動」という実際に音の出る作品を68年に制作しているが、それは、けっして突然変異的な試みではなく、彼女の仕事の底を流れる基音がたまたま表面に顔をのぞかせたにすぎない。
ここに来て、わたしは、宮脇が幾つかのヴァリエーションを制作した「LISTEN TO YOUR PORTRAIT」という銘文の入った金属や石の作品を思う。わたしの知るかぎり、これは宮脇が文字を作品の中心においた唯一の作品群であるが、なぜ「LOOK」ではなく「LISTEN」なのか。普通、肖像は見るものであってきくものではない。「あなたの肖像にききなさい」という呼びかけは、だから一瞬、見る者にとまどいをおこさせる。しかし、その奇妙な呼びかけを繰り返し刻んでいる事実は、ここに宮脇の、主体としての人間──「肖像」──への向き合いかたの原則が反映されていることを黙示している4)。
そう、彼女にとって、人間の「肖像」は見られるものではなくきかれるものなのである。あるいは《MEGU》の割れのように、見られるものの亀裂から振動してくる音なのである。これを存在論的な哲学として語りなおすことは可能かもしれない。ことに、存在の「開示」を語る時に、視覚的な隠喩とともに聴覚的な隠喩を多用したハイデガーのような哲学者の存在論と宮脇の「LISTEN」は近接した関係にありそうである5)。それを深く考える余裕は今ないが、二点、急ぎ足で触れておきたいことがある。
身体/言葉
一つは、ハイデガーも宮脇の作品も、聴覚を喚起することにおいて、伝統的な主体−客体関係(観者と作品の距離を置いた対面的な関係)の乗り越えへの契機を模索していることである。ただ、ハイデガーにおいては、その「きく」ということが、解釈学の伝統にのっとった詩の言語の経験と分かちがたくむすびついてい、「きく」ことの身体性は不問に付されたままである。
もう一つ。その意味では、ハイデガーの哲学を受けつぎながら、それを独自の身体論へと読み替えて、さらにそれを存在(あるいは世界)の「肉」という概念にまで鍛え上げていったフランスの哲学者メルロ=ポンティの試みに、宮脇の作品はより近いと考えられるかもしれない。しかし、皮肉なことにメルロ=ポンティは、身体という問題を自己の哲学の中心に置いたために、ハイデガーにおいて重要な位置を占めていた聴覚的な隠喩を、その言説の体系から置き去りにしてしまう。彼の哲学において焦点をなすのは、「見る−見られる」そして「触る−触られる」という感覚の相互性、反転性である(その点で、ミニマリズムの多くの彫刻家たちはメルロ=ポンティの哲学に深い影響を受けている)。
メルロ=ポンティは、西洋哲学の長い伝統を乗り越えようとしながら、まさにそのことで、その視覚中心主義的な伝統にやはり棹さしている。それに対して、宮脇の作品は、身体という問題に深く関わりながら、視覚、触覚を貫いて鳴っている聴覚を喚起することにおいて、メルロ=ポンティの身体論を斜めに貫き、少し違う場所へと突き抜ける契機を示しえているのではないだろうか。
このハイデガーとメルロ=ポンティの交差点にあって問題(盲点)になっているのは、実のところ、「きく」という行為が占める言葉と身体の「あいだ」の位置なのではないだろうか。それは、身体的な音/振動をきくことから言葉が生まれてくるというだけでなく、言葉にすでにやどる身体的次元をききなおすことでもある。身体にも言葉にも還元できない──あるいは身体と言葉の間を往還してやまない──その「きく」の次元は、だから、その両者の交差点にありながら対象化されえない不透明な揺れである。「うつろひ」はそんな見えない揺れからたちあがってきた作品群とはいえないだろうか。わたしは、「うつろひ」が、同じ素材を使った柔軟な構成によって世界を切り結ぶ仕方に抽象的な「文法」を見ると同時に、それがその都度「いま、ここ」における身体と世界の振動によって編みなおされているありように「歌」を聴く6)。
モダニズム/ポストモダニズム
真鍮やガラスの作品との連絡から言うと、《うつろひ》は、硬質な物質と光の戯れという意味で、連続したつながりを見せている。光が素材としての物質を内側から無化してしまう過程が、いわば極端にきりつめられた形で《うつろひ》には結晶している。細く撓みつつ中空を走る《うつろひ》の線は、その時々によって、光そして影そのものの軌跡となるだろう。それと同時に、虚の空間は、《うつろひ》そのものを成り立たせる媒体となる。
20世紀の彫刻史は、ある意味で、伝統的な「彫刻」概念への挑戦の歴史であるが、「虚」の空間をその内部にとりこむことも、その歴史の中で大きな意味を担ってきた。ピカソが1913年に制作した「ギター」のレリーフに始まり、タトリンの「コーナー・レリーフ」、ロシア構成主義の作家たち、ヘンリー・ムーア、第二次大戦後ではアンソニー・カロやソル・ルウィットなど、多くの作家が、虚の空間を作品の構成要素としてとりこんできた。そうした試みの数々を、単に見かけの類似でひとからげにすることはできないが、その一つの極限的な現れとして宮脇の作品を考えることはできるだろう。
しかし、伝統的な「彫刻」概念との関係ということで、よりわたしが気になるのは、実のところ、1960年代の後半以来、近代における彫刻の伝統の境界を超え、様々なかたちの「非彫刻」へと表現の場を拡張した一連の作家たちと宮脇の仕事の関係である。わたしは、ロザリンド・クラウスが「拡張された場における彫刻」という論において示した「(非)彫刻」の分野における「ポストモダニズム」の動向を念頭においているのだが、それと宮脇の仕事はどういった関係になっているのか7)。
クラウスは、1960年代、彫刻は自らの近代的なありよう(特定の場所や時間から切り離され自律した統一体としての)を徹底的につきつめた結果、ある回折点に達したという。つまり、内的なロジックによって決定されていたと思われた自己自身の本質が、60年代の彫刻実践を通じて、実は、建築ではない、風景ではない、というように、外との相対的な否定関係によってしか規定されないような何者かになってしまった。そして、もし、そのように「彫刻」が「建築」と「風景」という二項との否定的な関係によって規定されるしかないということになれば、当然、その二項を起点にして「彫刻」以外の関係性──つまり、建築でもあり風景でもあるというような──を考えることが論理的に可能になる。この論理的な可能性の場の「拡張」こそ60年代を通じて起こったことであり、ロバート・スミッソン、ロバート・モリス、マイケル・ハイザー、メアリー・ミスといった多くの作家たちの実践は、まさにその拡張の実験だったのだとクラウスは主張したのである8)。だから、「彫刻」というカテゴリーではとらえきれない作品のありよう──それぞれの仕方で風景と建築との新しい関係を模索するような──が、彼らの実践を通じて問われはじめたのだと。
クラウスは、この拡張の「論理」的な側面を指して、従来の彫刻の「素材」主義を超えるポストモダニズムの符牒とみなした。つまり、重要なのは、素材に内在する表現力ではなくて、風景や建築との新しい外在的な関係なのだと。したがって、彼ら「ポストモダン」な作家たちが使用する素材の恣意性は、その外在的な関係の優先の結果なのであって、モダンな立場から見ると目まぐるしく立場を変えているように見えるその実践も、ポストモダンな立場においては論理的に一貫したものなのだと、クラウスは言う。
わたしは、このクラウスの分析を、「彫刻」におけるポストモダニズムの出現に応えて、あらたな認識論的なフィルターを提示しえた画期的な論と思う。しかし、同時に、そのモダンからポストモダンへの移行が、素材的(あるいは本質主義的)な次元から構造論理的な次元へという飛躍的な切断のイメージによって描かれていることに少なからぬ不満を持っている。その間には、何というか、切断であると同時に継続であるような反転があるように思うのだが、そこの所に彼女の論はうまく切り込めていない。そして宮脇の《うつろひ》は、私の考えでは、まさに、その「反転」に位置する作品なのである。なぜか。
一つには、《うつろひ》が、風景の中に、そして建築の中に、どちらでもない要素として存在しつつそれらに作用を及ぼす(ポストモダンな)性質をもちながら、その構造は素材/媒体の性質への深い直観と洞察に根ざしているからである。場によってその現れと意味作用を微妙に変えながら、しかも、構造としての自律性を失わない。その意味で、《うつろひ》はモダンとポストモダンの結節点とも言える性質を持っている。いや、《うつろひ》が、真鍮やガラスの作品から連続して深まる素材との対話の中からたちあがってきた作品だとすれば、近代的な素材/媒体の性質への反省が、ポストモダンへの道筋を内側から開いたとも言える。
そういう風に考えてみると、モダニズムにおける作品の存立条件としての素材/媒体への自己反省の眼差しというのは、その「本質」を見いだすことでとどまることもある一方、それ自体をもまた反省の対象としてゆくという限界をしらない自己批判の運動をも内在させているのであって、クラウスが言う「論理的」な次元への飛躍は、そういう運動の徹底化と考えることもできるのである。モダンとポストモダンが、切断の見かけの下に密かな連絡を保持していると言うこともできるが、宮脇の《うつろひ》への転回は、わたしには、そこの道筋を照らし出しているように見えるのである。
《うつろひ》が、《MEGU》などを超えて、いよいよ「身体」という問題に深く踏み込んでいることは、《うつろひ》を体験した者には自明のことだろう。光、振動、虚の空間、すべての要素が、われわれの身体との関係の中で決定されているようだ。身体を誘い、拒み、貫き、結び、縛り、切り、そして包む。《うつろひ》の切りつめられた構造とその柔軟性、可動性は、前言した「振動」の感覚とともに、主客の二元的な関係の軛を超え、まさに、新しい身体の「場」そのものを現出させる。その一つ一つの場が経験する者に何を引き起こすか、それは一人一人によって違うだろう。
かつて、舞踏家田中泯が、《うつろひ》をステージにして踊ったことがあるが、舞踏家にとって、これほど刺激的な舞台設定もそう無いのではないか。さりとて、《うつろひ》は踊ることをそれぞれの人間に強要するわけではない。わたしにとっては、むしろ、その体験はささやかなもので、譬えて言えば、「歩く」とか「たたずむ」という日常的な経験をなにものかとして取り戻させる、そういうことである。踊る、歩く、たたずむ、そういう様々な人間の生きる姿勢のありように、失われた振動を再生させる、あるいは未知の振動を発生させる場としての《うつろひ》。その経験の中で、我々一人一人は、それぞれの肖像に「きく」ことをためされる。「あらぬもの」とは、その時きこえてくるあなたの肖像に他ならない。
to Top 「宮脇愛子ーある彫刻家の軌跡」展カタログ(神奈川県立近代美術館発行)より転載Copyright(c) The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, 1998
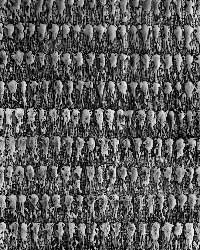
《作品》WORK 部分
1) Aiko Miyawaki ー Documents:A Pictorial Biography、美術出版社、1992年、p.14。

《作品 #11》WORK #11

《無題》Untitled 1964年
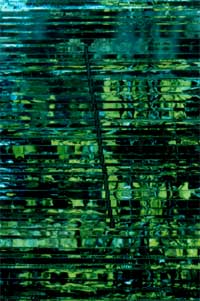
《メグ》MEGU 1972年

《メグ−77》MEGU-77 1977年
2) Charles Peirce, Logic as Semiotic:
The Theory of Signs,” in Philosophical Writings of Peirce, ed. Justus Buchier (New York: Dover Publications, 1955), pp.98-119.
「現在性」「同時性」という用語はパース自身のものではなく、わたしの解釈による。パースが強調するのは、インデックスにおける記号とそれによって指されるものの直接的な「隣接性」であり、そのために、インデックスは「盲目的な強制」によって記号関係を成立させるとも言われる。厳密に言うならば、この記号の三分法は、概念的なものであって、現実の記号作用は、つねにこの三種類の働きの混成と考えられている。
3)クラウスとバルトの写真に関する代表的な著作として次の2冊をあげておく。
ロザリンド・クラウス『オリジナリティーと反復』小西信之訳、リブロポート、1994年(ことにその中の「シュルレアリスムの写真的条件」そして「指標論:パート1、2」を参照)。
ロラン・バルト『明るい部屋』、花輪光訳、みすず書房、1985年。

《スクロール・ペインティング、白》
Scroll Painting: White 1975年

《作品「あなたの肖像にききなさい」》
Work “Listen to Your Portrait”
4)この「Listen to Your Portrait」という銘文を、わたしは当初「あなたの肖像を聴きなさい」と訳した。ところが、宮脇自身は、これを日本語として、「あなたの肖像にききなさい」というつもりだったと言う。ここには、興味深い問題が隠されている。というのは、日本語の「きく」という動詞が孕む二重性がここに露出しているからである。英語では、「ask」(意味の次元)と「listen」(音の次元)に分かれているものが、日本語では不分明に一つの「きく」という動詞の中にかさなりあっている(もちろん英語のlistenにおいても、listen to your fatherのような使われかたに、物理的な音を聴くのではなく「理解する」というニュアンスも時にこめられるが、日本語の「きく」はその曖昧さをさらに増幅している)。そのことが「listen(聴く)」に近すぎるわたしの訳に対する宮脇の違和感となって現れたのだと思う。この「きく」の二重性は、ハイデガーとメルロ=ポンティとの関係において展開した次のセクションの考察に、期せずして響きあうことになった。わたしが、「聴く」を「きく」という平仮名によって置き換えたのは、原稿を書き終えたあとのこの宮脇とのやりとりがあってからである。
5)ハイデガーにおける視覚的隠喩と聴覚的隠喩の、時に対立しあうような共存については、以下を参照。
Martin Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1993), pp.272-275.
6)註4)で触れた「きく」の二つの次元の問題と照らしあわせると、ここでわたしが「文法」というのは意味の次元、あるいは解釈学的な「了解」の次元に通じ、「歌」というのは声とリズムに代表される身体性に通ずるが、この二者が共鳴を起こしながらすれ違いをやめない、そういうものとしてわたしは、「うつろひ」の経験を考えている。
7)この論は、やはりクラウスの『反復とオリジナリティー』に収録されている。
8)したがって「拡張された場(Expanded Field)」という時の「拡張」には、実際に作品が置かれる場の拡張と、作品の成立条件の論理的な可能性の拡張の二つの意味が重ねられている。

《うつろひ》
Utsurohi 1983年 Photo: S. Anzai

《うつろひ》をステージにおどる田中泯
Utsurohi and danser Min Tanaka 1984年 Photo: S. Anzai