品切れ本を中心とした書評ページです。
多田智満子
1977年2月20日発行(増補版) 大和書房刊 196ページ
目次
第一部 鏡のテオーリア SPECULUM DE SPECULO
序/歩む鏡/向きあった鏡/見ることは見られること/まなざし/見ることは驚くこと/鏡の威光/鏡の迷宮/水鏡/大円鏡/因陀羅網/
第二部 鏡をめぐる断章 DE SPECULO QUOLIBET
眼の月/アルキメデスの凹面鏡/バックミラー考/世界の鏡/水鏡のエロス/鏡の墓碑銘/仏の鏡像/鏡と唐の詩人たち/影を失った男たち/神仙の鏡/跋
「それにしても、鏡とは、いかにも智満子さんの観照にぴったりのテーマだと思わざることを得ない。鏡のイメージは、それ自身、詩的であって哲学的であり、魔術的であって遊戯的であり、心理的であって物理的であり、神話的であって日常的であり、永遠的であって瞬間的であり、古典的であってデカダン的であるからだ。そして詩人としての智満子さんも、おそらく、この二方向を兼ね備えているのである。
レヴィ=ストロースから唐詩まで、ボルヘスから南方熊楠まで、レオナルド・ダ・ヴィンチから華厳経まで、ルイス・キャロルから江戸川乱歩まで、── 私たちは、このアリアドネーに似た閨秀詩人の手引きによって、鏡の国の迷宮にさまよい、その無際限の乱反射に目を奪われ、最後に、鏡の秘儀に参入することを得るだろう。鏡の秘儀とは? そのテオーリアには終りがないということだ」(「鏡のテオーリア」に寄す 澁澤龍彦)
多田さんは詩人であったともに、フランス文学の名翻訳者としても令名をはせていた。ユルスナールの『ハドリアヌス帝の回想』を多田さん以外の人が翻訳していたら、本邦のユルスナール受容は現在のようにポピュラーな広がりをもっただろうか。さて、そんな名翻訳者なのだから、彼女の学識は西洋文学において優れているのだろうという勝手な思いこみがあったのだけれども、しかしそれは迂闊な誤りだった。多田智満子という人物は広く古今東西の書物を渉猟し、その博引旁証は和漢洋のさまざまな文典からなされている。冒頭に澁澤龍彦が本書に寄せた跋文の一部を引いたが、まったくその引用の「無際限な乱反射」には、目の眩む思いがする。特に意外にも、仏典や中国文学に対する多田さんの造詣の深さは相当なもので、澁澤氏は多田さんと昵懇の間柄だったらしいが、東洋通のエッセイストとして、密かに一目置いた存在だったのではないだろうか。ともかく、平明ながら叡智のレース編みのような端然としたスタイルは、エッセイを読む真の面白さにわたしたちを酔わせてくれる。
人はなぜ鏡を見るのか
「人間はみな〈歩む鏡〉なのだ」、フッサールを引用しつつ、そう著者は指摘する。「神といえどもこの世界については、我々の経験と同じような、つねに完結することのない射映の系列という形をとらない経験をすることはできないであろう」。── つまり、三次元の空間のなかで生きる私たちは、同時に二点以上の位置を占めることができない以上、私たちの〈経験〉する外的事象は、私たちの「眼」という一面鏡に継続的に映された像にすぎないということだ。ここで著者は自問する。それでは、「とりわけ人間が鏡的な意識をもち、すぐれて鏡的な存在であるのはなぜだろう?」── このような問題意識から、著者は鏡の国の哲学的なアリスとなって、わたしたちを不可思議な鏡像世界へと導いていく。
「鏡をのぞきこめば、鏡の中の私が私を見ており、さらに他人は私を、私が鏡の中の私を見るようにしてきているということ」── 人間とは「見る者」であると同時に「見られる者」でもある。そして鏡は「見る私」から「見られる私」への回路を開き、「見る/見られる」の宿命的な反復運動を意識に強制する。ここで、著者は思いがけない方向へ話題を転じる。
「仏教でいうところの悟り乃至解脱とは、この〈見る=見られる意識〉からの脱出であり、仏陀(すなわちめざめた人)となって輪廻の業を離れるとは、この〈見る/見られる〉の輪廻を脱して、もっと次元の高い〈眼〉を持つようになることだ、という、仏教の現象学的解釈(!)も成り立つであろう」。(p.27)
このように、鏡についての考察は、徐々に仏教的な色彩を帯びはじめるのだが、その結論部ともいうべき第一部末尾の二章「大円鏡」と「因陀羅網」は、何度読んでも迫力に満ちている。
映し出される〈時間〉
「大円鏡」では、仏の至高の智慧のはたらきのひとつの、大円鏡智ということがテーマとなる。大円鏡智とは、よく磨かれた鏡が万象を映しだす如く、仏の曇りない絶対智には万象が明らかに顕現していることを指す。西洋での鏡は、もっぱら意識の屈折と複雑化を象徴するものとして扱われることが多いと、著者は指摘したあとで、東洋では(とりわけ仏典のなかでは)、意識と欲望からの解脱成就のために鏡の比喩が多く用いられると述べる。ところで、「神といえどもこの世界については....」という先述のフッサールの言葉を、もう一度読み返してみてほしい。この言葉に関連して、著者はこう話題を進める。
「『神といえども...... 』、このフッサールの表現は強力な説得力をもつ。しかし、これを、『仏といえども...... 』と言い換えることはできないのだ。なぜかというと、仏典の中では、仏の大円鏡智は、万象をくまなく映すばかりではなく。十世を同時に映す、と説かれているからである」。(p.89)
過去・現在・未来の三世のおのおのに、過去の過去、過去の現在、過去の未来というように三世を配すると、全部で九世になり、その上、この九世を総合した一世を考えると、合計十世になる。華厳経では、この十世が同時に顕現して、縁起を成じていると説く。同時に、というのは、これらの過去や現在・未来がさらに相互的・円環的につながりあっていると考えられているからだ。 大円鏡智とは、すべての「時間」が映し出される鏡なのだ。
映し出される〈存在〉
さらに、すべての「存在」を同時的に映し出す鏡へと話題は進む。「因陀羅網」とは、神々の帝王インドラ(帝釈天)の宮殿を荘厳している宝網のことで、その網のひとつひとつの結び目ごとに宝珠がはめこまれている。その珠は「無量にして算すべからず」。そしてその一粒々々が他のすべての珠の影を映し、さらには、一珠の中に現れる他の一切の珠の映像のひとつひとつが、各々他の一切の珠を映すというふうに限りがない。しかしながら、
「諸法皆空とはいえ、存在は無数の鏡像となって分散し無化するのではない。逆に、一つの存在は他のすべての存在を反映することで、言うなれば、『一微塵のうちに十万世界を見る』ことで、無限の重みをもち、世界内での縁起の網のひとつの結び目としての役割を負うのである」。(p.95)
「大円鏡」といい、「因陀羅網」といい、しかし結局、すべては鏡に映された虚像に過ぎないのではないかという懐疑論は、華厳哲学とは無縁であるらしい。なぜなら、すべてが幻であると知りながら、それにもかかわらず大恐怖に陥ることなく、救済のための行にはげむことのできる人こそ真の菩薩大士である、と般若経は結論しているからだ。
つづく次の一節は、本書の中でも論理の飛翔と速度に満ちてすばらしい。 「それにもかかわらず、というこの実存的な飛躍によって、すべての鏡像は無機質の冷たさから癒され、すべての幻影の人に暖かい血が通いはじめる。無限に増殖した映像の大群を総体的非現実から救いとるものは、理論的には華厳哲学の弁証法にちがいないが、それに活きた血肉を与えるものは『不条理ゆえに信ず(クレド・クイア・アブスルドム・エスト)』というテルトリアヌス風の信念と、キェルキェゴールの『にもかかわらず(トロッデム)』とを、大乗的遠近法のもとに統一したような、この菩薩の不退転の決意なのである。 (略) すべては映像の戯れでありながら、自らも映像の一つとして進んで鏡中に入ることにより、人は鏡を超ええたということができよう」。(p.98)
このような硬質な詩的思考をたどっていると、ボルヘスの『アレフ』などは、案外ささやかな寓話にすぎなかったのではないかと思えてくる。ともあれ、少々、形而上学的な話題に終始しすぎたかもしれないが、本書の第二部「鏡をめぐる断章」は、もっと気軽に遊ぶことができるので、ご安心を。とにかく、多田さんという詩人は、HAPPY FEWのための詩人文学者であった。
本書は、ちくま学芸文庫に収録されていたこともあるが、惜しいことに現在は品切れ。著者の他のエッセイ集としては『魂の形について』が、白水Uブックス(白水社刊)で入手可能。
by takahata: 2005.08.05
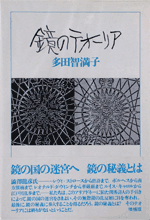
|
エッセイ・評論篇 01『先師先人』竹之内静雄 |
|